「なにかに使える」を分析する
私たちが普段よく口にする「なにかに使えるかも…」というセリフ。
そんな身近な何気ない「なにかに使える」が、実は生活にすごく困ったことをもたらす、という事を考えていきたいと思います。
目次
「なにかに使える」は誰しも思うこと
テレビでゴミ屋敷の取材をしているのを見ていると、必ず見かけるシーンが、レポーターがゴミ屋敷の主人のそばに行き、誰が見ても明らかにいらないと思うようなモノを手に取って、
「これはもういらないんじゃないですか?」と聞くシーンです。
すると主人から出てくるセリフはほぼ100%
「ダメだ‼︎ なにかに使えるだろ‼︎」です。
こんなゴミ屋敷の主人がよく使う「なにかに使えるだろう」は実はゴミ屋敷の住人だけではなくて、私たちが暮らしていて普段よく口にする言葉です。
今日はこんな「なにかに使えるだろう」という言葉がもたらす生活への影響を分析していきたいなと思います。
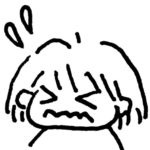
『影響を分析とかってなんか今日は難しいことなんだね』
いえいえ、そんなに難しいことではないので、安心して聞いてください。
「なにかに使える」は生活のあちこちにひそんでいる
「なにかに使える」は私たちの生活の様々なところに点在しています。
靴を買ってきて箱がついてきた時
友達から何かもらって紙袋がついてきた時
お菓子が食べ終わって空箱が残った時
何かを整理しようと思って買って来たケースのサイズが合わなかった時
私たちは「なにかに使えるだろう」とついつい思ってしまう。
「なにかに使える」はどういう性質か考える
じゃあこの「なにかに使える」と思っているモノの本当の意味を少し考えていきたいなと思います。
自分が持っているモノの中で、「なにかに使える」と思ったモノは次の5つのうちどこに入ると思いますか。
- よく使っているモノ、お気に入りのモノ
- たまに使っているモノ
- 滅多に使わないモノ
- 「この瞬間」が来たら使おうと保管しているモノ
- いらないモノ、ゴミ

『うーん、4かな❓』
パッと見そう思ってしまいますよね。でも、よーく考えみましょう。
「なにかに使える」と言う事は、今現在は使いみちを思いつけていないということになります。
もし将来の使いみちが思いあたるのであれば「なにかに使える」ではなくて「この時にこんな風に使おう」と思はず。
これが4の「この瞬間が来たら使おうと保管しているモノ」です。

『じゃあ、5のいらないモノ でもないと考えると、4と5の間くらいかなって思うけど。
そうですね〜私もその辺かなぁって思います。
『やった〜当たった〜』
実は、その4でも5でもない、宙ぶらりんな状態が困ったことを引き起こすんですよ。
「なにかに使える」が持つ中途半端な立ち位置が不便を呼ぶ
「なにかに使える」モノはこの先どう使ったらいいか思い浮かんでないモノです。
そんな使いみちを思いついていないモノを保管するとき人はどんな場所に置くと思いますか。

『え、あ、どこだろ、使いみちが思いつきやすいように目につくところに置くかな」
そうなんです。
これが「なにかに使える」が持つ危険な性質。
そういうモノは、目が届くところ、手に届きやすいところを選んで置きますよね。
だって使いみちが分かっていないのだから、普段からよく見えるところに置いておいて使いみちを考えなければいけない。
でも本来そんな目が届く、手に届きやすいところに置くべきなのはどんなモノですか❓
1や2のよく使うもの、使いみちがしっかりとあるものを置くべき。その場所を「いらないモノ」に限りなく近いモノが侵食するのです。
便利な場所に、使う予定がないモノが入り込むんです。
では、 4「この瞬間」が来たら使おうと保管しているモノ は、どこに置きますか❓
例えば、
「いらなくなったシャツのボタンを少し置いておいて、ボタンが飛んだ時に使おう」と思っていたら、ボタン置き場を考えて、邪魔にならないところに置きますよね。
これが「用途がある」ということ。用途があると、目につくところに置く必要がない。
用途が未定だから、生活の邪魔をする。
5の「いらないもの、ゴミ」に限りなく近いものが生活の便利な場所に置かれてしまう。
それが「なにかに使える」の困った部分なんです。
この言葉をつぶやき続けると、大切なモノと、使いみちがないモノが混在して、ものすごく不便な状態になっていきます。
何でもかんでも捨てて欲しいとは思いません。
私たちは昔に比べ減れば良くなったとはいえ、不安定な世界で生きています。
だから全部捨てることなんかできない。そんなの当たり前なんです。
ただ、「なにかに使える」の危険性を知っておいて欲しいと思います。
「なにかに使える」と思った時は、用途をしっかりその時に考えてください。
思いつかない時は、保管期限を決めましょう。
あるいは、「なにかに使える置き場」を作って、そのスペースの中でやりくりするのもいいかもしれません。
生活の便利な場所から「使っていないモノ」を排除すべきなのだ、という事を考えてルール作りをするのが大切だと思います。
